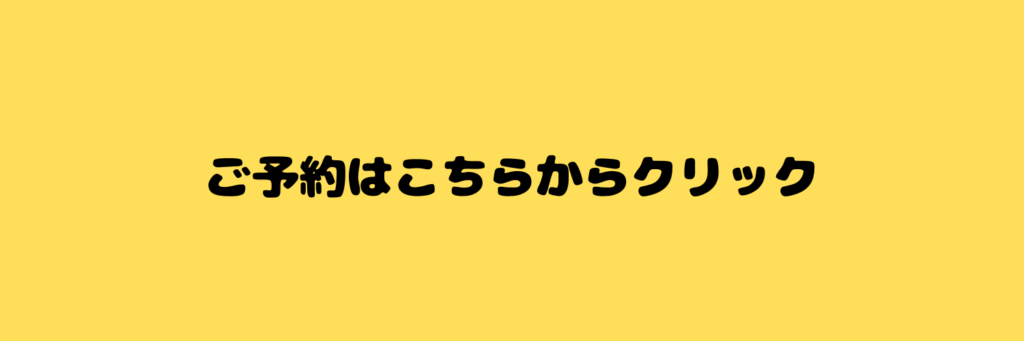はじめまして。
まあるい気持ち こころのサポートルーム
🌻ふじさわともこです。

1972年 東京都調布市にて誕生。幼いころから「まわりの人の気持ちを大切にしたい」と感じる子どもだった。
人の顔色を見て動いたり、誰かの悲しみに敏感に反応したり——
“優しすぎる性格”は、いつしか「がんばりすぎてしまう」自分をつくっていった。
30歳で結婚。 その後、長男を出産。
息子が、成長していくにつれて、多動や落ち着きのなさ、遊びに集中できない部分が見え隠れする。
息子が、高校生の時にASDとADHDの診断が出る。
保育士を長年経験してきたこともあり、母になる喜びの一方で、「ちゃんとした母親でいなければ」と自分を追い込み、 完璧を目指すあまり、少しの失敗も許せない日々だった。
第2子は長女。敏感で、感受性の強い子。
私自身もHSP(繊細な気質)だったこともあり、娘の不安や涙に強く共鳴してしまい、
一緒に落ち込んだり、必要以上に心配したり——
“子どもと自分の境界線”が分からなくなっていた。
子どもが増え、少し長めの育児休暇を取る。2人合わせて3年4か月。家事、育児に追われる毎日。
「ちゃんとしなきゃ」と思うほど、心が疲れていくのに、「助けて」が言えず、一人で抱え込んでしまう日々が続く。
育児休暇の間は、地域のつながりをとだえまいと、積極的に近くの保育園や子育て広場、児童館など育児のイベントには積極的に参加していた。ママ友も出来る。自分は仕事に復帰をすることを考えると今のママ友達とはお付き合いがなくなるのかと孤独感を感じていた瞬間もあった。
その後、仕事復帰。久しぶりの仕事に力が入り、保育園に子どもを任せきりにしていた自分もいた。毎日が無我夢中だった。
私は仕事をたんたんとこなす日々が続いた。
そして、息子が高校、娘が中学に行き始めたあたりから、それぞれの生きづらい場面が多くなり、目の当たりにする。
仕事と、プライベートの両立は私には無理だと感じた。
気分も落ち込み、どうしていいかわからない日々。
涙が突然あふれるように出て来てしまったり、足が動かなくなってきてしまい、休職。その後退職となる。
そんな中で出会ったのが、心理学だった。
休職中、カウンセリングを受けていた。
その時にあるカウンセラーの言葉が私の人生の転機を作ってくれた。
「自分の人生は1度きり。好きに生きていいんじゃない?」
とまどいもあったが、ある日、散歩中青空を見上げていると
ふと。
「自分の人生を歩んでいいのだ」と感じたのだ。
「こんなに心が軽くなるなんて」——
それは、長いあいだ張りつめていた心が、少し緩んだ瞬間でした。
そこから少しずつ、自分の気持ちを見つめるようになり、
心理学を学びながら、「私が変わると家族も変わっていく」ことを実感したのだった。
心理学・カウンセリング・発達支援・アロマ心理などを学ぶ中で、
「発達障害」、「HSP」や「HSC」という言葉に出会う。
人との関わり方、考え方、感じ方、行動の仕方に偏りや苦手さが現れる状態。
敏感で共感力が強い——その気質は、弱点ではなく“人を思いやる力”だと気づいたとき、
長年の生きづらさが少しずつほどけていった。
自分の気質を理解できたことで、子どもへの見方も変わってきた。
「この子はどうしてできないの?」ではなく、
「この子はどう感じているんだろう」と思えるようになり、
家庭の空気がやわらかく変わっていった。
がんばりすぎてしまうお母さんへ。
子どものことで頭がいっぱいになって、自分のことはいつも後回しになっていませんか?
子どもを変えようとするより、まずお母さん自身の心が整うことが大切です。
自分を責めず、ありのままを受け入れられるようになると、
自然と家族にも穏やかな風が流れはじめます。
私自身の体験が、その一歩を踏み出すきっかけになれば——
そんな思いで、今の活動を続けています。
現在、「まあるい気持ち こころのサポートルーム ふじさわともこ」として、
発達障害・不登校のご家庭や、子育てに悩むお母さんへの
アロマカウンセリングと心理サポートを行っています。
香りと対話の両面から、
「心がまあるく整う時間」をお届けできるようサポートしています。
【さらに詳しいプロフィールはこちら】

【やんちゃではあるが、消極的な部分もある子ども時代~】
1972年。東京都生まれ。父・母・姉・私の4人家族。やんちゃで、元気いっぱい。負けず嫌いで棒を見つけるといつも振り回していた。その反面、教室の空気や表情の揺れに敏感で、授業では、本当にわかっているもの以外は手を上げられないなどの一面があった。
~孤独を回避するために空気を読んでいた中、高校生時代~

居心地の良い子、憧れる子…と心で分類しつつ、誰に対しても空気を乱さない振る舞い。先回りの配慮で「みんなと仲良く」を保ち、孤独を避けていました。
「音楽」と「体育」だけは楽しくてしょうがなかった。
中高一貫校に通っていた私は、「ソフトボール部」に入部。一緒に過ごしていた先輩との関係も、話す時には常にどきどきしてしまい、あまり話せるようではなかったように思う。
そう言いながらも、部長を務めながら、ソフトボールに熱中する日々を送っていた。

【期待に応えたい気持ちのある進学、就職~】
高校時代、当たり前のように進学を考えていた。教育熱心な母のアドバイスもあり、保育の短期大学へと進む。免許取得後はある自治体に勤務。事務職、幼稚園を経て保育園に努める事となる。幼稚園勤務の時は、質問できず、自分一人の考えで動き、気持ちを抱え込む日々が続きました。何か質問すれば、追い込まれるようなことを言われ、気持ちはどんどん落ち込んでいく。もともと保育園勤務を希望していたので、2年勤務をした後は、保育園に異動する。保育園は、幼稚園よりも明らかに働いている人数が多かった。職員、パート勤務の先生、朝、夕方だけ働く先生などなど。さまざまな人がいて、自分にアドバイスをしてくれたり、相談をしてくれる先生もたくさんいた。少しずつ、自分を取り戻してきたのを感じてきた。5,6年に一度は異動する保育園。時には、「自分の意見をきちんと出せ」と言わんばかりのアドバイスをしてくる時もあった。自分を出し切れない環境に行き詰る時期もあった。

【結婚、出産へ。母になる重さ】
30歳で結婚。妊娠もする。母となるという事。不思議な感じでもあり、大いなる喜び、妊娠への不安など、様々な気持ちが入り混じる。喜びもつかの間。流産をしてしまう。
そこで、自分をとても追い込んだ。わたしのせいだ。私が安静にしていれば、こんなことにはならなかったと言う気持ちになる。

【保育士から母へ――新しい学びの始まり】
しばらくの間は、気持ちは切り替わらなかったが、1年後、長男を授かる。少しの間、仕事からは解放されるのだとほっと一安心でもあったが、同時に母になると言う不安感もなかったと言えばうそではない。
長男出産の際、首の所でつっかえてしまい、時間がかかったり、出産後、病院でも無呼吸発作を起こし、私と同時に退院出来ず、だが、数日後に退院。家族と子どもの生活が始まるのだった。
成長の面においては、保育士をしていたこともあり、育て方に不安はなかった。
でも、子どもって育て方がわかるだけでは、ダメなのだと育てながら痛感することはたくさんあった。

あちこち、走り回り、興味をそそられる息子、繊細な娘。ほぼワンオペで過ごした子ども時代~
主人は休みが不定期の仕事をしていたので、休みの日以外の子育てはほぼワンオペの生活が続く。2,3歳のころの息子は、きょろきょろ見回し、興味のあるものを見つけると、すぐ走ってどこかに行ってしまう。後ろにいる親の事を振り返ることもあまりなかったように思う。娘は不安なのか、私のそばを離れず抱っこばかりだった。夜泣きも多く、大きな声で泣いていた。夜中に泣く度に、近所迷惑にならないかと冷や冷やした時期を覚えている。
子育てを一生懸命にしながらも、いつもまわりの事を気にしていることが多かった。
近所のママ友は本当にいい人ばかりだった。でも、自分は仕事復帰をする状況でもあり、仲を良くしたい反面、あまり親交を深めると寂しさが募るので、自分の中で制限をかけていたような気がする。
近くに義理の父母の家があり、少し遠いが実家もあった。仕事が始まってからは、当番もあり、朝早かったり、夜になってしまったりなどの時は、子どもの面倒を見てくれていた。
本当に感謝してもつくしきれない。

【実母の一言、まわりの一言を気にする日々】
自由奔放な息子が、成長していくにつれて、実母が私につぶやく場面が多くなった。
「こうした方がいい、ああした方がいい」と押し付けてくる。
言ってくれる言葉は、世間一般で言えば、正論ではあるかもしれないが、我が家は我が家の育て方があると主張しても、わかってもらえないこともあり、強く言い返せない自分がもどかしくてしようがなかった。
娘はおとなしいながらも、私に主張をしてくる子どもだった。その姿を見て、「甘やかしている」と厳しい言葉を浴びせる時もあった。
実母は本当はとても優しい人だっただけに、違う1面が出てしまうと、私の心もモヤモヤすることが多かった。

【それぞれの生きづらさを抱える日々。その時親の私は・・・。】
両親共働き。子ども達それぞれに悩んでいる事はたくさんあったと思う。でも、私は仕事しか目に入っていなかった。子どもは勝手には育たないのに・・・。
それぞれの特性はあるとは言え、まわりの環境や雰囲気を感じ取る子ども達。
私が、毎日のように遅く帰っても、ごはんが手作りでなくても一切文句を言う事はなかった。兄は高校生。娘は中学生。それぞれが、本当に辛い時期を迎えていた。
① 息子の場合
公立高校に通う息子。もともと中学から一緒に行く子は誰もいなかった。
なかなか学校に慣れず、友達も出来なかった。高校2年の時に転機が訪れる。同じクラスに友達が出来た。とても、うまの合う友達だったようだ。その友達を介して、4人も友達が増えた。毎日が充実しているかのように思われたのが、高校3年生の時。周りは受験モード。その雰囲気を感じ取った息子は違和感を感じ始めた。まわりの雰囲気に追いつけず、どうしていいかわからなくなってしまった。
夜中ずっと起きて、ゲームやユーチューブをし続ける毎日。当然朝は起きられない。布団から出られず、学校を休む日数が増える。学校から留年しそうだとの声もかかり、母としてはどうにかしてあげたいと思った。
まずは、私ではなく、専門の先生に息子の心の声を聞いてもらおうと、息子に「行ってみないか」と声をかけてみる。「行ってみる」と即答だった。ほっとした安心感もあったが、そこまで追い詰められていたのかと涙が止まらなかった。心療内科に足を運ぶ。先生と話をして、検査をすることになった。
その検査は、2時間近くの長い検査だったので大丈夫かなと心配もあったが、なんとかこなす。2週間後に結果が出る。ASDとADHDだった。本人の表情はとても清々しかった。「僕の苦しさはこの特性からきているんだ」。
そこからは、大学への進学を決め、合理的配慮を受けての受験をした。受験までは私も手伝いながら準備を進めた。でも、前を向いて頑張る息子を見ながら、一緒に受験をしている気分になってうれしいものがあった。
大学へ無事入学。頑張ろうと前向きな息子。頑張りすぎて、エネルギーを失ってしまう事もしばしば。息子が、信頼している臨床心理士の方の配慮もあって、頑張れてはいたが、エネルギー切れになると、大学を休んだりもする。途中、休学も体験。今は、自分のペースで大学に通っている毎日を過ごしている。
② 娘の場合
もともと、いろいろな事に感じやすい娘は、小学生の時に友達に言われたある一言から自分の思いをうまく出せなかったり、殻に閉じこもってしまう事が増えてしまった。地元の中学に入学し、新しい環境に慣れない娘は、朝、「行きたくない」のつぶやきが増え、行けない日が増えてきた。
最初のうちは、どうにか行かせようと必死になるが、朝、布団から出れないことも増え、泣いている姿を目の当たりにしていたら、何も言えなくなってしまい、娘の様子を見ていくことにした。そのうち、まったく行かなくなってしまった。担任の先生とは連絡は取り、定期的な連絡はしていた。家では、ひたすらユーチューブの毎日だったが、言いたい思いを抑え、様子を見ていくことにした。
1年生の途中で、学校の先生に進められ、WISCと言う検査をする。結果は、グレーゾーンだった。
2年生になる。体育祭があり、娘は参加したいと言い出した。でも、それからまた行かなくなってしまった。私は学校に行かないのであればと、フリースクールに行かせたり、塾に行かせたりと試みるが、一時的に心は開いても、行きたくないアピールが出て、結局やめる事に。そんな生活が続いた。娘なりにどうにかしなければと思っているが、何か違うなと感じていたのだと思った。
2年生の夏前、中学校内にある特別支援級の体験を学校の先生よりすすめられる。それが、娘にとっての意欲をかきたてたようで、支援級に行きたいと言ってきた。母親にしてみれば、普通級に戻れるのならば、戻って欲しいと願いもあったし、学校の先生たちも普通級に戻ってくるものだと思っていた。
支援学級の体験は、あくまでも学校に戻れる手段だと。でも、娘は本気だった。夫婦で相談をする中で、娘の様子を見ながら、娘の思いを尊重してあげようということになる。2年の途中から転級となり、特別支援級に行く。担任の先生たちも、娘と向き合い、本当によく関わってくれていたと感じた。時も過ぎ、高校受験の時期となる。
特別支援級になっても、学校を休んだりもしていた娘だったが、高校選びは慎重だった。
選んだのは定時制。学校を見て、授業などを見たりする中で、決定打のようなものがあったようだ。
もともと、集団の中に入っていくのが苦手な娘。電車に乗る時も人に背を向けて乗っていた。その娘が、受験の日に、人ごみにもまれて受験をしにいくたくましさを目の当たりにし、娘の本気度を感じる事が出来た。現在は高校2年生。娘にとって環境もいいのか、頑張って毎日通っている。
③ 私の場合
出産、産休、育休を経て仕事復帰。子供を保育園に預け、本当に無我夢中の毎日を過ごしていた。私自身、仕事と子育ての両立はとても厳しいものだったのに、子どもの為に、家庭の為に、仕事をすることを選んでしまったのだ。もし、途中で仕事を辞めていたならば、子どもの運命も変わっていたのかもしれないと感じる。勤務年数も長くなってくると、責任も増え、やらなければいけないことも増えてくる。全ての事において、きちんとやりきらなければいけない、人に頼むことが出来ないことが、仕事と家庭のバランスが取れなかった最大の原因だったと思う。
ある日、どうしていいかわからなくなり、涙が止まらず、仕事にも行けなくなってしまった。そこから、休職。仕事に復帰をしようと感じたこともあったが、休職中にカウンセリングを定期的に行っていて、そのカウンセラーの言葉がきっかけとなり、退職を考えるようになった。
「何にこだわっているの?これからは、自分のやりたいことを選んでもいいのだと思いますよ。だって、人生は1度きり。家族はいても、自分の人生なのだから。」と。
最初は、その言葉をぼーっと考えている時間も続いていたが、ある天気のいい日。散歩をしようと外に出て、ふと、空を見た。とてもきれいな澄んだ青空だった。
その時。「そうだ。やることをしてみよう。退職しよう」と急に思った。幸いなことに、退職の話は、家族に事前に話していて、最初は納得はしてくれていなかった主人だったが、「自分のやりたいこと、やってみなよ」と応援してくれたのだ。子どもたちも応援してくれた。
家族の理解もあり、今の道に進めたのだと思っている。

【これからのカウンセラーとしての人生】
心理学を学び、カウンセリングに臨む毎日。私自身、家にいる時間も増え、家族もそれぞれの姿を応援できるようになりました。仕事でも、自分に自信を持ち、繊細さを強みに仕事を進めています。
カウンセラーとして大切にしていきたい思いは、「安心して自分を語れる場所をつくること」。
誰かの心が少しでも軽くなり、自分を受け入れられるようになる -そのきっかけをそっと渡せる存在でありたいと願っています。

【私にしか出来ない支え方】
・専門家ではなく「先輩ママ」として寄り添います
→ 当事者としての体験があるから、わかる気持ちがあります。
✅ 「親の心のケア」を最優先に考えます
→ 子どもを変える前に、まずお母さん自身が癒されることを大切に。
✅ 一方的なアドバイスはしません
→ 解決方法を「教える」のではなく、一緒に見つけていく対話型です。
✅ 自然体で話しやすい空間
→ アロマの資格も活かした、やさしい雰囲気と安心感を大切にしています。
をモットーにしています。

まあるい気持ち こころのサポートルーム ふじさわともこ。
発達特性・不登校支援、HSP/HSCサポート、アロマを取り入れたカウンセリング、先生・保育士向け相談。まずは体験から安心してお話しください。
いつでもお待ちしています。
長文に目を通して頂きありがとうございました。